(12月15日、東京朝日新聞) (13日上海発)
日本と清国の交渉について、協定の調印は15~16日頃に行われる見込みである。その主要な条項は次の通りである。
第一条
関東半島(旅順・大連などのある地域)の租借期限は、1923年3月をもって終了とする。
第二条
長春以南の東清鉄道(いわゆる南満州鉄道)は日本に引き渡す。ただし、調印の日から10年間を期限とし、その後は清国が買い戻すことができる。ただし、もしロシアが保有していた他の区間が清国のものに戻る場合には、期限を待たずに日本は清国の買戻しに応じる。日本は枝線(支線)を敷設してはならない。
第三条
鉄道の保護のために日本軍の守備兵を置くこと。
第四条
日本軍の撤退は18か月以内に完了すること。
第五条
日本の軍用電信線(通信網)は10年間設置を許可する。その後は清国が買収すること。
第六条
牛荘(ニューチワン)、奉天(瀋陽)、安東県(丹東)、吉林、寛城子(長春近郊)などに日本領事館を設置し、保護兵を配置すること。また、今後開かれる都市についても同様にする。
第七条
日本は上記の地に銀行を設置できる。
第八条
日本人の居住は、開かれた市場(開港・開市場)に限定される。
第九条
牛荘の税関は清国に返還する。ただし、これまでの収入は精算のうえ清国に引き渡すこと。税関長の任命は清国政府が行う。
第十条
奉天から30里(約12キロ)以内にある撫順炭鉱の採掘は日本に許可する。ただし、その他の鉱山は許可しない。
第十一条
日本は軍票(戦時中に発行した軍用紙幣)を速やかに兌換(現金と交換)すること。
第十二条
塩および木材の取扱いは従来の規定に従うこと。
第十三条
奉天にある日本の軍政署は、撤兵と同時に撤去すること。
第十四条
もし条約の解釈や実施に異議が生じた場合は、日英同盟の期間内に日清両国が委員を選んで解決する。ただしその有効期限は10年間とする。
(この条項の電報文は不明確)
以上の各条項は、ほぼ確実な情報と見られている。
1. 時期と文脈
この記事は1905年12月、つまり日露戦争の講和条約(ポーツマス条約)締結直後のものです。このとき日本は、ロシアから譲り受けた遼東半島租借権・南満州鉄道の権益などについて、清国(中国)との間で正式な承認・整理を行う必要がありました。その交渉が本記事にある「日清交渉」(正式には「満洲還付条約交渉」または「満洲善後条約」)です。
2. 主な目的
日本と清国の交渉目的は以下の通りです:
• 日本がロシアから譲り受けた満洲・遼東の租借地・鉄道権益を清国に正式に認めさせること。
• 同時に、日本が戦時中に駐留させた軍隊や通信施設の撤収・処理の条件を定めること。
結果として、1905年12月22日に「日清満洲善後条約(清国側名称:満洲新約)」として正式に調印されました。
3. 実際の「日清満洲善後条約」の内容との比較
この記事の条項は、実際の条約内容と非常に近いです。ただし、一部の期限(例:租借期限・買戻し期限)は新聞報道の段階では誤伝もあります。
実際の条約では:
• 関東州租借期限:25年(1928年まで)
• 南満洲鉄道の権益:日本が管理、清国の買戻し権なし
• 日本軍の駐屯・鉄道守備権:認められる
したがってこの記事は、正式調印前に上海から電報で伝えられた「草案段階の情報」とみられます。
4. 歴史的意義
この条約によって、
• 日本は**南満州鉄道(満鉄)**を経営する権利を獲得し、
• 遼東半島(関東州)を租借地として統治することが確定しました。
これは、日本の満洲進出の第一歩であり、のちの
• 関東都督府の設置(1906年)
• 満鉄経営・満洲利権の拡大
• 満洲事変(1931)や満洲国建国(1932)への布石
につながります。
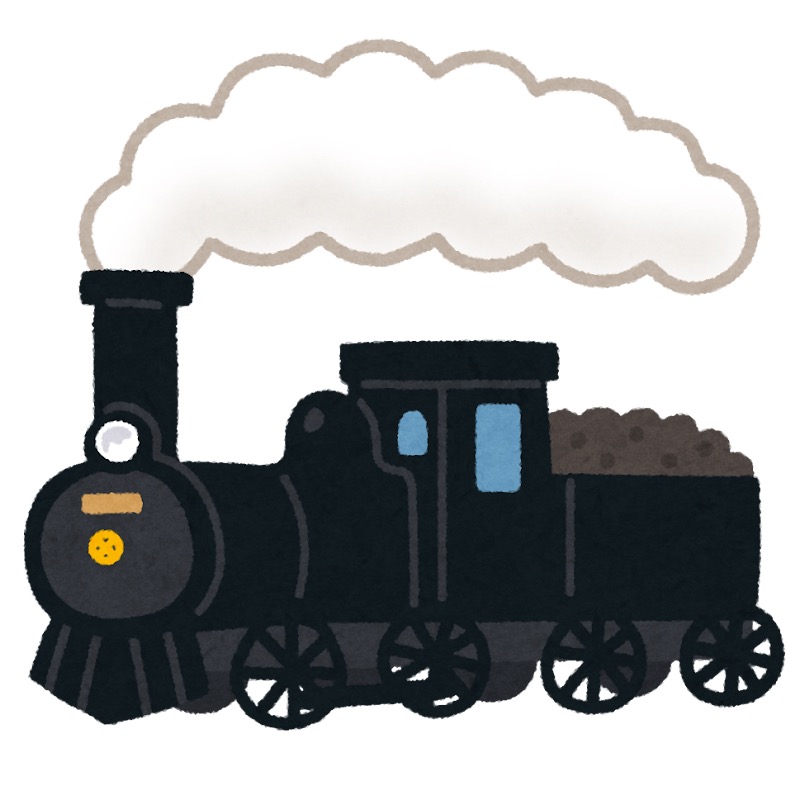


コメント