(11月23日・東京朝日新聞)
本日行われた第32回大日本衛生学会(※全国の医師・衛生学者が集まる学会)では、啓学博士**緒方正規(おがた まさのり)氏と、学士石原喜久太郎(いしはら きくたろう)**氏の連名によって、「越後地方の恙虫(つつがむし)病」および「秋田地方の毛虱(けじらみ)病」の病原に関する研究が発表される予定である。
この研究は、両氏が本年7月、北越地方(新潟県周辺)で流行していた恙虫病の現地調査を行い、実験を重ねた後、京都に帰ってからもさらに専心して研究を進めた結果、これまで学者の間でも不明であった病原体をついに発見したというものである。今回の発表は、その成果を正式に公表するものであるという。
「恙虫(つつがむし)病」とは
「恙虫病(つつがむしびょう)」は、ダニの一種(ツツガムシ=タテツツガムシなど)によって媒介される感染症で、発熱・発疹・リンパ節腫脹などを起こす、日本特有の風土病でした。江戸時代から東北・北陸地方(特に新潟・秋田・山形)で「越後熱」「秋田病」などと呼ばれ、致死率の高い謎の病気として恐れられていました。
明治期に入り、欧米の細菌学・衛生学が日本に導入されると、この病気の原因究明は国内の感染症研究の最重要課題の一つとされるようになります。
緒方正規と石原喜久太郎の研究
記事に登場する緒方正規(1863–1906)は、東京帝国大学医学部出身の細菌学者で、のちに岡山医科大学教授として知られた人物です。彼は日本の伝染病研究の先駆者の一人で、赤痢菌・コレラ菌などの研究でも功績を挙げていました。石原喜久太郎はその共同研究者で、京都帝国大学医科大学に所属していました。
二人は1905(明治38)年夏、新潟・秋田地方で流行した恙虫病・毛虱病の現地調査を行い、採取した病原を京都で培養・顕微鏡観察し、病原体が寄生性の微小なリケッチア様生物(のちに「リケッチア・ツツガムシ」)であることを突き止めました。
この記事は、その発見を日本衛生学会で初めて発表する直前の報道です。
学術的意義
緒方らの研究は、日本人が自国の風土病を科学的に解明した初期の成果の一つであり、明治日本の医学が欧米に追いつきつつあることを象徴するニュースでした。
のちにこの研究は、
• 1920年代に川村麟也らによってさらに進展し、
• 1930年代にリケッチア・ツツガムシ(Rickettsia tsutsugamushi)として国際的に認知され、
• 戦時中(太平洋戦争期)には日本軍の衛生対策上の重要感染症として再注目されます。
つまりこの記事は、恙虫病の病原研究の出発点を伝える極めて初期の記録です。
当時の科学的文脈
1905年は、
• コッホ(細菌学の父)の理論が確立してから約20年、
• 日本でも北里柴三郎や志賀潔が活躍した細菌学黄金期です。
そうしたなかで、「地方の流行病の病原を実地調査で解明する」ことは、国家的衛生行政(公衆衛生政策)の象徴的成果として報道価値がありました。そのため、この記事のように朝日新聞が科学ニュースとして報じるのは、「日本の医学はここまで来た」という文明開化的な誇りを示すものでした。
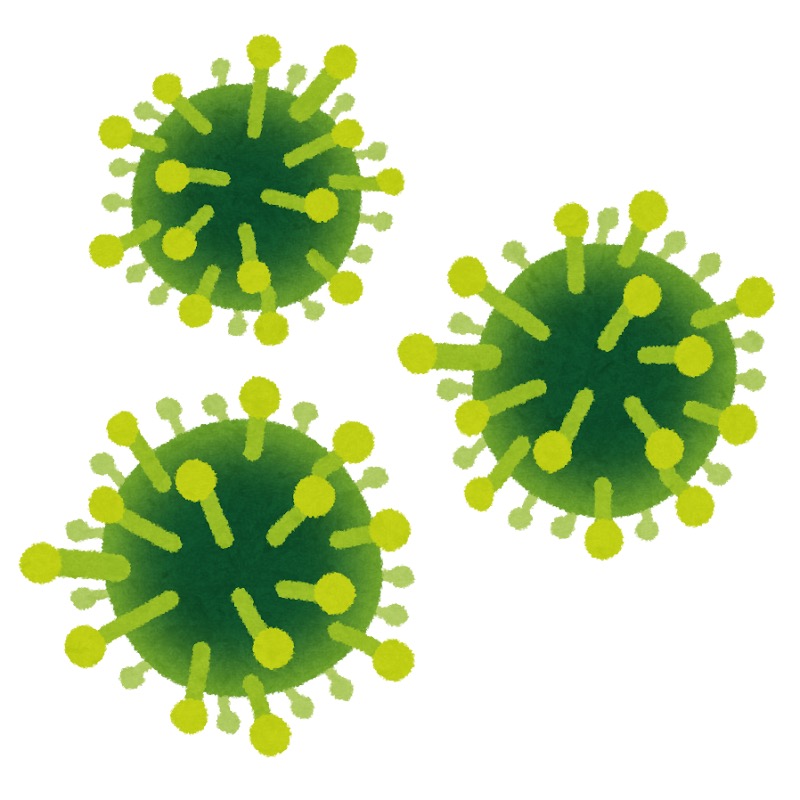


コメント