(11月23日・官報)
勅令
朕(ちん:天皇)は、韓国に統監府および理事庁を置く件を裁可し、ここにこれを公布する。
明治三十八年十一月二十二日 内閣総理大臣 兼 外務大臣 伯爵 桂太郎
勅令第240号
明治三十八年十一月十七日、日本帝国政府と韓国政府との間で締結された協約(=第二次日韓協約)の第三条に基づき、韓国の京城(現・ソウル)に統監府を設け、また、京城・仁川・釜山・元山・鎮南浦・木浦・馬山その他必要な地に理事庁を置き、この協約に定められた諸般の事務を取り扱わせる。
〔附則〕
本勅令による統監府の職務は、当分の間、従来の帝国公使館が行い、理事庁の職務は、従来の帝国領事館が引き続き担当するものとする。
時期と位置づけ
この記事は、「第二次日韓協約(乙巳条約)」の公布(1905年11月17日締結)を受けて、日本政府がその協約に基づいて韓国統監府を正式に設置したことを示す公文書です。この勅令の公布(11月22日)は、日本が韓国の外交権を奪い、事実上の保護国化を進めるための行政的手続きの第一歩でした。
第二次日韓協約(乙巳条約)の概要
項目 内容
締結日 1905年11月17日(明治38年)
日本側全権 伊藤博文(特派全権大使)
韓国側全権 朴斉純・李完用ら(高宗の同意なしに署名)
主な内容 韓国の外交権を日本が掌握し、京城に日本統監府を設置すること
この条約により、
• 韓国は独立国家としての外交権を喪失し、
• 外交・通商などの対外関係を日本政府が全面的に管理する体制になりました。
つまり、ここに見える「統監府」「理事庁」は、韓国を保護国として統治する日本の出先機関だったのです。
「統監府」と「理事庁」の役割
組織 設置場所 主な役割
統監府(とうかんふ) 京城(ソウル) 日本が韓国を監督・指導する最高機関。初代統監は伊藤博文。
理事庁(りじちょう) 京城、釜山、仁川、元山、鎮南浦、木浦、馬山など 各地の日本領事館を拡充した機関地方行政・警察・通信・貿易などを実質的に掌握。
この制度の下で、韓国政府は名目上の自主権を保ちながらも、実際には日本の行政指導に従うことになりました。つまり、「統監府=韓国統治の司令部」「理事庁=地方行政機関」として機能します。
歴史的影響
• 翌年(1906年)2月、伊藤博文が初代統監に就任。
• 韓国の内政に日本の顧問官が入り込み、財政・軍事・司法・通信などを日本が管理。
• 1907年には韓国軍の解散、
• 1910年には「韓国併合条約」によって完全な植民地化へと進みます。
したがってこの勅令は、韓国併合への中間段階を制度的に確立した決定的な一歩と位置づけられます。
史料としての意義
この「勅令第240号」は、形式上は「天皇の名による韓国行政機構の設置命令」ですが、実質的には日本政府(桂太郎内閣と伊藤博文)が主導した植民地支配の法的根拠の一つです。新聞記事として『官報』に掲載されたのは、それを「国内外に正式に公布する」ための告示でした。
明治政府はこのように、外見上は合法・条約的な形式を整えながら、韓国を段階的に日本の統治下に組み込んでいったのです。


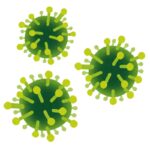
コメント