(明治38年11月10日、東京朝日新聞)
大山巌(おおやま・いわお)満洲軍総司令官は、昨夜、次のような特に丁重な勅語(天皇のことば)を拝受した。
勅語
卿(けい=あなた)は、外地における重大な任務を受け、大軍を指揮して、遠く異国の地に長く在った。
いまやついに平和が回復するに至った。
朕(ちん=私)は、卿に会って長期にわたる戦況の報告を聞きたいと思う。
よって卿はすみやかに総司令部を率いて帰国し、凱旋して復命せよ(任務の報告を行え)。
この勅語を受けて、大山総司令官はすぐに奉答(返答)の電報を天皇に送ったとのことである。
このように格別に丁寧な勅語を拝受したことから、帰国の出発時期を当初より少し早め、本月(11月)中にも大連を出発することになるのではないかと伝えられている。
この新聞記事は、日露戦争終結後(1905年=明治38年)に、大山巌が満洲からの帰還を命じられた際の報道です。
◾ 時期の背景
• 日露戦争は1904年2月に開戦し、1905年9月のポーツマス条約で講和が成立しました。
• 戦場である**満洲(中国東北部)**では、大山巌が日本軍の総司令官として全軍を統括していました。
• 講和成立後も軍の撤収・整理などが続き、大山はしばらく満洲に留まっていましたが、ここでようやく**天皇から帰国命令(凱旋命令)**が正式に下ったのです。
◾ 勅語の意味
• 「卿其れ速かに総司令部を率み凱旋復命せよ」とある通り、天皇が大山に対して「戦争が終わったから、早く帰って報告せよ」と命じています。
• 「殊域に在ること茲に久しく(遠い異国に長くいた)」という表現から、約1年半にわたる前線統帥への労をねぎらう意味も強く含まれています。
• このような**丁重な言葉遣い(優渥なる勅語)**は、戦功を高く評価したことを示しています。
◾ 大山巌について
• 西南戦争では西郷軍を討ち、後に陸軍大将・元帥として日本陸軍の重鎮となった人物。
• 日露戦争では総司令官として奉天会戦などの大勝を指揮し、日本の勝利に大きく貢献しました。
• 帰国後は、明治天皇から親しく謁見を許され、戦後処理・軍功表彰などにも関わっています。
◾ 社会的意義
• この報道は、戦勝ムードの中で国民に「戦争が完全に終わった」という安心感を与えるものでした。
• 同時に、大山ら軍上層部への敬意と天皇の「親政的威光」を強調する、戦後の国威高揚的な記事でもあります。
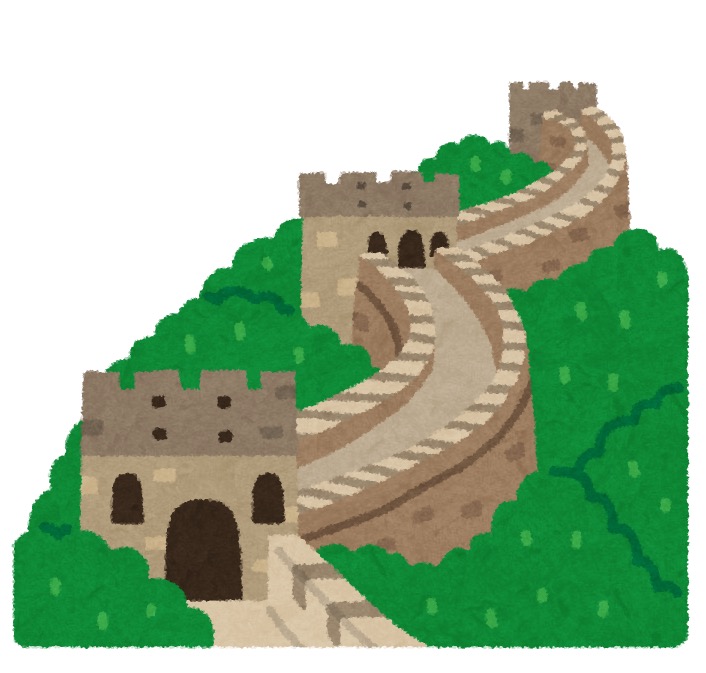


コメント