(明治38年〔1905年〕10月30日、東京朝日新聞) (28日 北京発)
山東省高密県に駐屯していたドイツ守備隊は、常に清国人と衝突し、さまざまな面倒な問題を引き起こしていた。ところがドイツは今回、意外にも清国の要求を受け入れ、まもなく撤兵することになった。同時に、北京と天津の間にある楊村およびもう一か所からも守備隊を撤去することを決定し、現在その準備を進めている。また、駐清ドイツ公使も撤兵が終わり次第帰国する予定だという。ドイツのこの行為は、清国に恩を売り、将来別の要求を出すための布石であると考えられている。
続報
駐清ドイツ公使は外務部に対し、ドイツの山東省における行動について、近ごろ種々の中傷的な噂を流す者がいるが、ドイツは清国の主権を尊重し、かつ平和を目的とするため、本日より撤兵する、と宣言した。さらに、開門鉄道沿線からも撤兵することを述べた。清国は近ごろ非常に進歩し、もはや義和団事件のような再発の恐れはないと判断するため、これも清国の主権を尊重して撤兵するのだ、と宣言した。
1. 義和団事件後の外国軍駐屯
• 1900年の義和団事件で列強が清を攻撃・鎮圧したのち、北京議定書(1901年)によって各国は清国内に軍を駐留させる権利を得ました。
• ドイツは山東省(膠州湾租借地、青島を拠点)を勢力圏として軍事的・経済的な進出を強めていました。
2. ドイツ軍と清国人の衝突
• 山東省などでは、ドイツ守備隊が現地住民としばしば衝突し、摩擦を引き起こしていました。清国政府は撤兵を要求していましたが、列強の駐屯は「清の主権侵害」の象徴でした。
3. ドイツの「撤兵宣言」
• 本記事は、ドイツが清の要求を「意外にも」受け入れたと報じています。
• ただし記事後半でも触れているように、これは単純な譲歩ではなく「清に恩を売り、後に別の要求を通しやすくするための政治的布石」と解釈されています。
• 実際、ドイツはこの後も山東省支配を強化していき、完全に手を引いたわけではありません。
4. 国際関係の背景(1905年当時)
• 日露戦争が終結(1905年9月)し、東アジアの勢力図は再編されつつありました。
• 日本は朝鮮半島での優越を確立しつつあり、ロシアは後退。
• ドイツは東アジアで孤立を避けるため、イメージ改善を図りつつ、中国市場での経済的立場を維持しようとしました。
• この撤兵宣言は「中国の主権尊重」という建前を示すことで、国際世論にアピールする狙いもあったと考えられます。
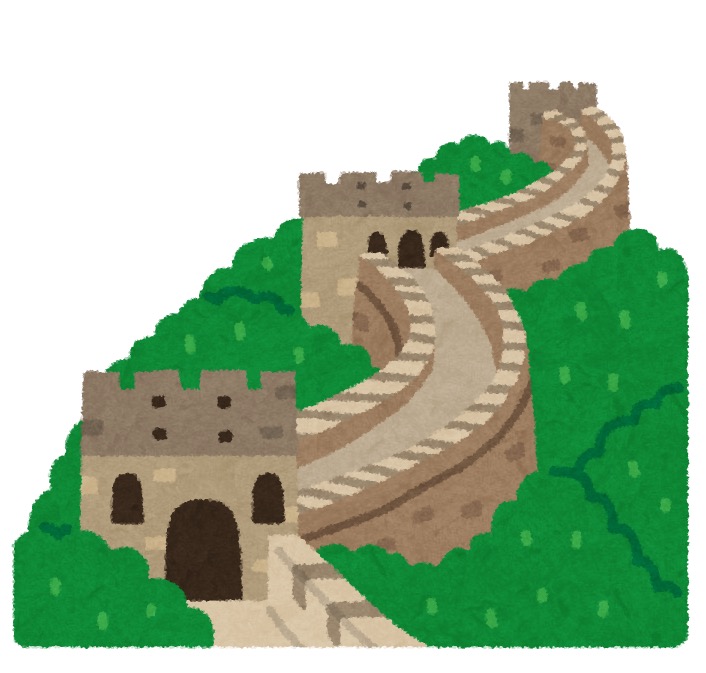


コメント