(明治38年〔1905年〕11月13日、東京朝日新聞)
日本とアメリカとの間で、新たに著作権(版権)に関する条約が、一昨日、東京において締結されたという。近いうちに正式に公表される見込みである。
これまで、アメリカは万国著作権条約(ベルヌ条約)に加盟していなかったため、日本ではアメリカ人の著作物を自由に翻刻(コピー)・出版することができていた。しかし、今後はこの日米版権条約によって、
他の加盟国と同様に、著作者の許可を得るなどの正式な手続きが必要となることになった。
◾ 時代の背景
この記事は、日本が国際社会の中で「文明国」としての地位を確立しつつあった時期の報道です。19世紀末から20世紀初頭にかけて、日本は西欧列強と対等な関係を築くため、軍事・外交だけでなく、法律・文化・知的財産制度でも国際基準への整合を進めていました。その一環として、外国著作権の保護制度の整備が重要視されていたのです。
◾ 「版権(著作権)」とは
当時の「版権」とは、今日でいう「著作権(copyright)」のことです。明治期の日本ではまだこの言葉は定着しておらず、「出版権」「翻刻権」などと呼ばれていました。
◾ 日米版権条約の意義
🔹 それまでの状況
当時、アメリカは国際的な著作権保護制度(ベルヌ条約, 1886年)に加盟していませんでした。そのため、日本国内でアメリカの本や音楽を自由に翻刻・出版することが可能でした。例えば、英語のベストセラーや教育書をそのまま日本語訳したり、あるいはそのまま模倣印刷することも法的には問題にならなかったのです。
🔹 条約締結の目的
日本は文明国の一員として国際的信用を高めるため、アメリカとの二国間著作権保護条約(日米版権条約)を結びました。これにより、アメリカ人の著作物も日本で保護され、一方で日本人の著作物もアメリカで保護されるようになります。つまり、「相互保護」の原則が導入されたわけです。
🔹 条約の効果
日本で出版業を行う業者にとっては、「勝手にアメリカの書物を再版できない」=出版の自由が制限される不利益がありました。しかし、国際的には「文化・知的財産を尊重する国家」として評価され、日本の文明化・法治国家化の象徴ともなりました。
◾ 世界的な流れ
19世紀後半、ヨーロッパでは「著作権保護=文化国家の証」とされており、それに倣って日本も1899年にベルヌ条約に加盟しています。
今回の記事は、日本がアメリカと個別に著作権条約を結んだという点で重要です。(アメリカがベルヌ条約に加盟するのは、ずっと後の1989年です。)
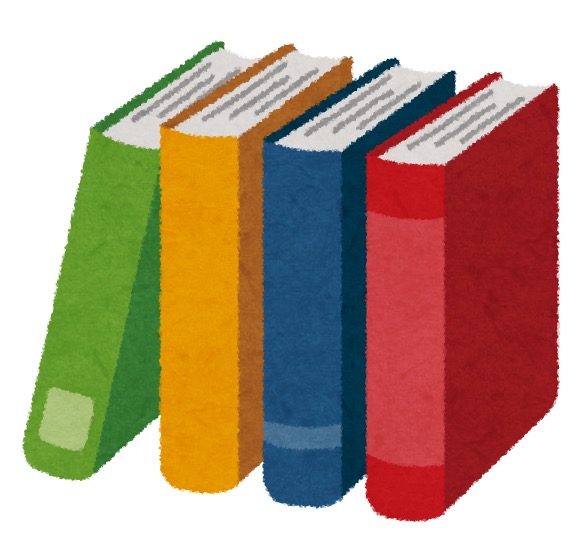


コメント