(1905年9月13日、報知新聞)
(9月12日 大本営発表)
本日12日午前9時までに到着した各方面からの報告を総合すると、戦艦三笠は、11日午前0時20分ごろ、大橋付近において火災が発生した。すぐに佐世保港に停泊していた各艦艇や、陸上の諸部隊から派遣された消防隊が加わり、懸命に消火に努めたが、火元を突き止めることができなかった。
同0時37分、ついに後部弾薬庫の一部が爆発を起こし、水線下の左舷外板に破孔が生じた。そのため浸水が激しくなり、同日午後2時30分、艦底が海底に着いて動けなくなった。
火災の原因については、艦体を引き揚げて損害の詳細を調査しなければ判明しないと思われるが、直ちに査問委員会を設置し、調査に着手した。
(以下省略)
三笠は日本海海戦(1905年5月)の旗艦で、東郷平八郎が指揮を執った「連合艦隊の象徴」的存在でした。
日本の勝利を決定づけた艦であり、国民からも「英雄の船」として特別視されていました。
1905年9月11日深夜、佐世保軍港に停泊中に火災が発生。
弾薬庫に引火して爆発を起こし、艦は沈没。
乗員300名以上が死亡または行方不明とされる大惨事となりました。
日比谷焼打事件(9月5日)の直後で、国民の動揺は収まっていない時期に、「勝利のシンボル」である三笠が、戦後まもなく国内の港で爆沈したことは、国民に大きなショックを与えました。
一部では「ロシアの陰謀ではないか」「内部の不注意ではないか」といった噂が飛び交いました。
三笠はその後、引き揚げられて復旧し、再び現役艦として使用されました。
しかしこの火災・爆沈は、日露戦争の熱狂から一転して日本社会が直面する不安や不信を象徴する出来事といえます。
現在、三笠は横須賀に記念艦として保存されています。
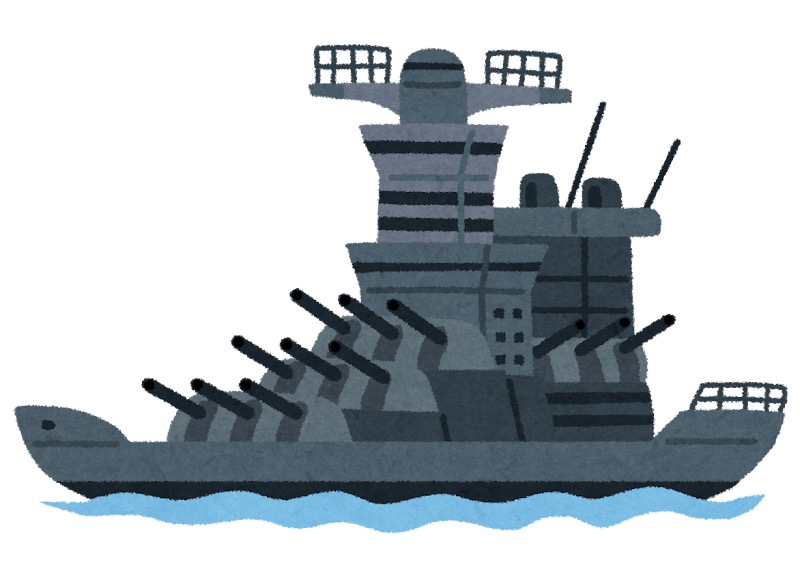


コメント