〔明治38年10月6日、東京朝日新聞〕
日露戦争の影響で、昨年(明治37年)2月以来、横浜港には各国の軍艦が寄港しなくなっていた。そのため、各地に散在する「チャブ屋」はどこも不景気を嘆いていた。
ところが、講和が成立し、多少軍艦の入港も見られるようになり、さらに近くはイギリスやアメリカの軍艦が多数入港する予定だという。そこで青息吐息であったチャブ屋の主人たちは、腕の立つ女を雇い入れ、外国人を呼び込み、これまでの不景気を挽回しようとあれこれ策をめぐらしている、とのことである。
1. チャブ屋とは
• 「チャブ屋」とは、外国人船員を主な客とした遊興施設。
• 主に横浜や長崎などの外国人居留地に隣接した地域にあり、芸妓遊び・飲食・売春などを提供していました。
• 「チャブ(chab)」は英語の “chap”(男・やつ)が訛ったもの、または “chop”(印判・証)の意味からきたとされ、外人相手の「遊郭風飲食店」を指す俗称でした。
2. 日露戦争と軍艦寄港の減少
• 日露戦争(1904–1905)の間、日本近海は緊張状態にあり、外国軍艦の入港は極めて制限されました。
• そのため、外国人水兵を主な顧客とするチャブ屋は客を失い、不景気に陥ったのです。
3. 講和後の変化
• 1905年9月、ポーツマス条約で講和が成立。
• 戦争の緊張が緩み、外国艦船が再び日本の港に寄港することが可能になりました。
• 特にイギリスやアメリカは日本の同盟国・友好国として積極的に艦隊を派遣しており、横浜の繁華街もその経済効果を期待しました。
4. 社会的視点
• 新聞記事は「商売っ気」をやや皮肉を込めて報じています。
• チャブ屋の存在は、当時の横浜の国際港湾都市としての裏の顔を象徴するものでもありました。
• 外国人相手の歓楽産業は港町の経済を支える一方で、風紀問題や衛生問題を引き起こし、しばしば世論や当局の規制対象になっていました。
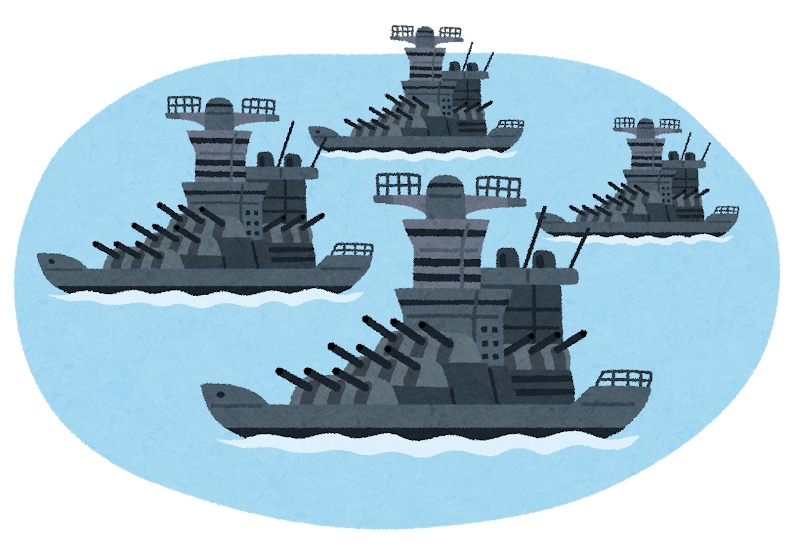


コメント