(12月2日付 時事新報)
ソウルの南大門(現在のソウル駅付近)から平壌までの区間で普通列車の運行を行っていた京義鉄道は、このたび12月1日からさらに平壌と新義州の間の営業を開始した。これにより、京義鉄道は初めてソウル(南大門)から新義州まで、旅客・貨物の運輸を全面的に行うことになった。同鉄道は、軍事上の必要に迫られて工事を急いだため、やや粗雑な工事となった箇所があり、橋梁などいくつかは改築の必要がある。しかし、これらの補修工事は営業を行いながら順次進めていく予定であるという。
1. 京義線とは
「京義線(けいぎせん)」は、京城(ソウル)と義州(新義州)を結ぶ鉄道で、現在の韓国・北朝鮮を縦断する主要幹線の一つです。「京」は京城(ソウル)、「義」は新義州を指します。
• 総延長:約440km
• 南大門(ソウル)~新義州(北朝鮮の国境都市)
• 現在の北朝鮮側では、平壌を経て中国との国境・丹東へ通じる重要路線。
2. 建設の目的と経緯
当時(1905年)は、日露戦争(1904–1905)終結直後。日本は朝鮮半島を事実上の保護国化しつつあり、軍事的・経済的な支配体制の確立を急いでいました。
• この鉄道は、もともと朝鮮政府が着工したが、資金難で進まず、日本政府・軍が引き継ぎました。
• 戦争中は兵站(へいたん:軍需輸送)に不可欠であり、日本軍の占領鉄道として整備が進みました。
• 1904年に京城〜平壌間、1905年に平壌〜新義州間が完成し、この記事で「全線開業」が報じられています。
3. 「拙速」の理由
記事中にある「軍事的必要に迫られ功遅を避け拙速を取りて工事を施した」という部分は、とにかく早く開通させるために粗い工事で済ませたという意味です。日露戦争の最中、日本はロシアの鉄道網(シベリア鉄道など)に対抗して、軍の移動・補給路としてこの鉄道を急ぎ建設したため、耐久性や仕上がりよりも「速度」が優先されました。
4. 歴史的意義
この京義線の全通によって、日本は
• 朝鮮半島北部(新義州)から満洲へと通じる軍事・経済回廊を完成させ、
• 翌1906年の「韓国統監府」設置(伊藤博文が初代統監)以降、植民地化のインフラ基盤を確立しました。
つまり、この「全線開業」は単なる交通ニュースではなく、朝鮮支配の完成段階を象徴する出来事でした。
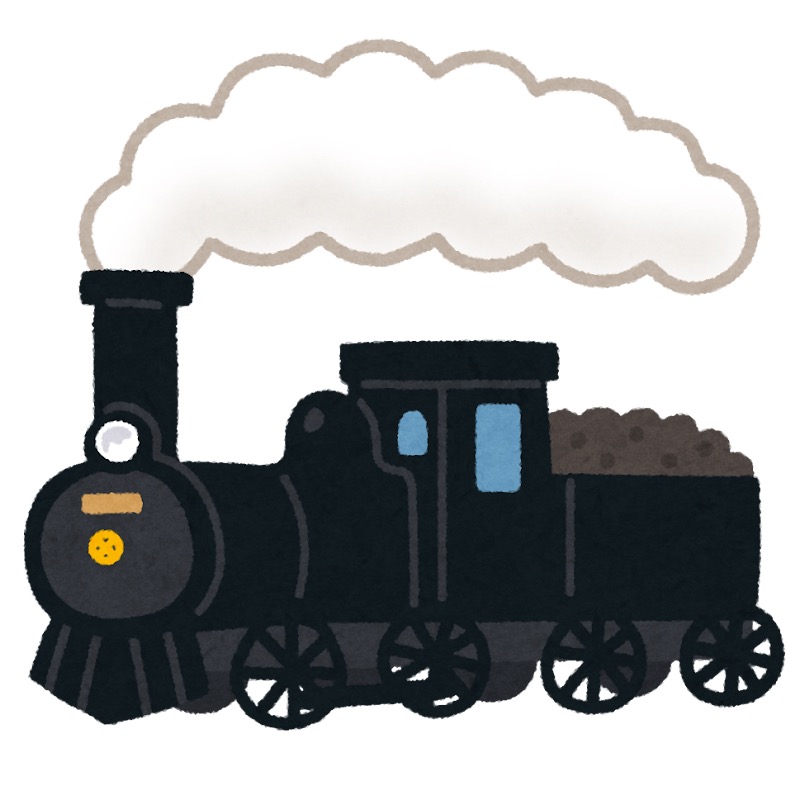


コメント